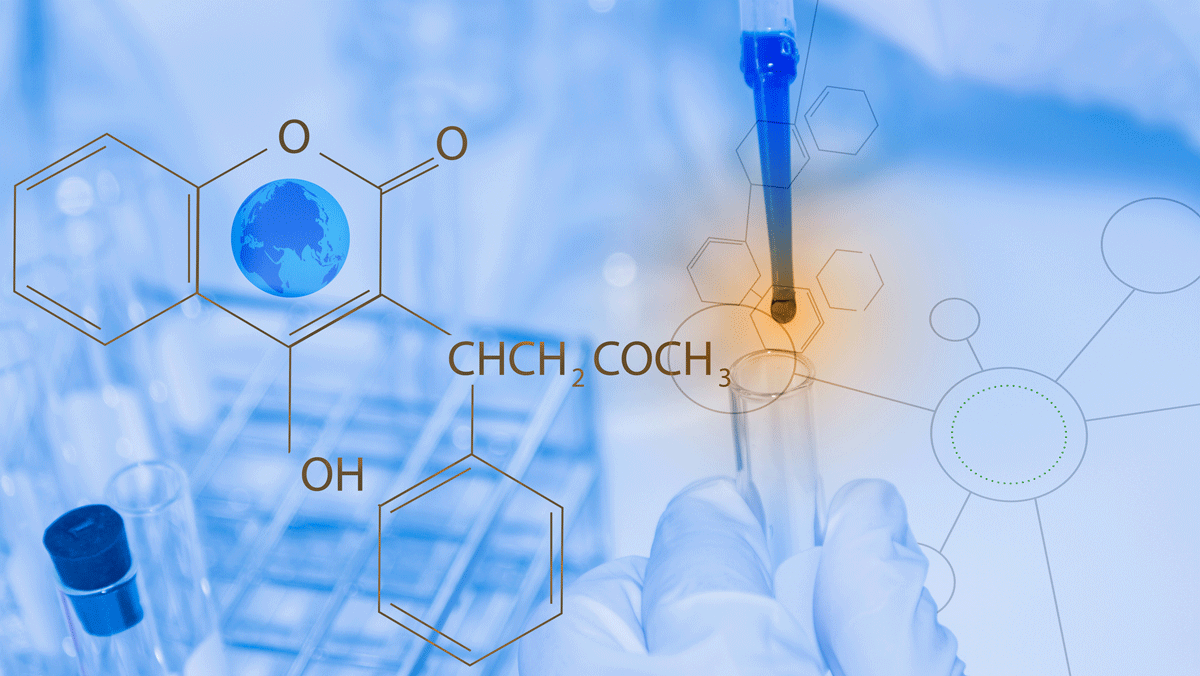創薬研究の最難関・臨床試験とは 『医薬品クライシス』著者・佐藤健太郎氏が語る、医薬研究職の世界 Vol.4

元製薬会社の研究職として、創薬研究に携わっていた佐藤健太郎氏による連載、第4回をお届けします。今回は前回に引き続き、創薬研究の過程についてです。その長い道のりにどのような関門が待ち受けているのか、実際の経験を交え、医薬研究職のリアルを語ってもらいました。
◆
前回は、研究所でさまざまの過程を経て、医薬候補化合物が出来上がるまでのプロセスをお話ししました。しかし、これはあくまで「候補」でしかなく、実際にこれらが「医薬品」として世に出るまでには、まだまだ長い道のりが待っています。最大の難関ともいうべき、「臨床試験」を通過しなければならないのです。今回はこのあたりの話をしてみましょう。
臨床試験の前に待ち受ける「量産化研究」
研究の初期段階で、タンパク質や細胞を用いた実験をするには、化合物は数ミリグラムから数十ミリグラムもあれば十分です。マウスなど小動物を用いる段階になればもう少し量が要るようになり、毒性試験などをおこなう段階では数十グラムから数百グラムの量が必要になります。
毒性試験用のサンプルは大量合成しなければならず、それだけでも大変ですが、それに加えて不純物が結果を狂わせることのないよう高い純度も求められます。実験の日程なども決められていますので、間に合うように合成するのは実験者にとってプレッシャーでした。筆者も、特許書類作成と毒性実験用サンプルの合成さえなければ、合成研究者はずいぶんいい商売なのだけど、とよくぼやいたものです。
さらに臨床試験の段階になると、これとは桁違いの量が必要になります。医薬の投与量は体重に比例しますので、人体に用いる場合にはマウスやラットの場合の数百倍を用いねばなりません。それを何百人、何千人に投与するわけですから、医薬候補化合物がキログラム単位で必要になります。当然、とうてい一人の研究者の手には負えません。
そこで、プロセス化学という専門部署の出番となります。大スケール実験に伴う安全性、コスト、安定供給などの問題を解決することが、彼らの使命です。本当に有機合成化学を知っていないと務まらないプロフェッショナル部隊であり、創薬研究を長年おこなったベテラン研究者がこちらに移るケースも多くあります。
医薬品の運命を左右する「製剤研究」

突き詰めれば、医薬品の実体は一定の構造を持った化合物です。ただし、「構造が同じならどのように投与しても効き方は一緒」というほど、医薬というものは単純ではありません。
薬を利用する立場からすれば、注射や点滴よりも飲み薬のほうが楽なのは当然のことです。しかし飲んだ薬が患部にたどり着き、効き目を表すまでにはさまざまな関門が待ち受けているのです。
まず医薬は、固体の状態から水に溶けてくれなければ、体内に吸収されません。本来どんなに効果がある化合物でも、結晶の安定性が良すぎて全く溶けなければ、砂を飲んでいるのと同じです。こうして溶けた化合物が、腸や肝臓などの生体膜を通過して血流に乗ることで、初めて効果を発揮し得ます。
錠剤、カプセル、顆粒、粉末などさまざまな形状の医薬が存在しているのは、その医薬の力を最高に引き出すための工夫です。たとえば錠剤の場合、有効成分以外にもさまざまな添加物を加えて固めてあり、これによって吸収性や安定性を最適に保っています。また、水なしで飲めるよう、口の中でさっと崩壊するような錠剤もありますし、胃酸では崩れず、腸ではじめて溶ける錠剤というものも存在します。味が悪くて飲みにくい薬も、製剤法によってカバーすることが可能です。
医薬化合物の結晶化工程も、条件次第で分子の詰まり方が異なった結晶ができ、それぞれ溶解性の良し悪しがありますので、最適な条件を煮詰めなければなりません。また、少量製造するときは問題なかったのに、工業規模で大量に作ると問題が発生するようなケースもあります。こうした、文章化しにくい細かなノウハウを積み重ねて、最適の形状を選び出し、作り出すのが「製剤研究」です。
優れた化合物であっても、製剤法ひとつで無に帰することもありますし、既存の医薬が製剤の改良で新たな命を吹き込まれることもあります。地味にも見えますが、製剤研究は医薬の運命を大きく変えうるほど重要な領域です。
創薬研究の最難関「臨床試験」

医薬品創出の最難関となるのが、臨床試験の段階です。多数の人間で、医薬候補化合物(ここからは治験薬と呼ばれます)の安全性と有効性を確認するわけですから、極めて慎重な仕事が必要になりますし、費やすコストや時間も莫大なものになります。
臨床試験は、いくつかの段階に分かれます。
・ 第Ⅰ相試験
治験薬を、いきなり病気で弱っている患者さんに投与するのはリスクが高いので、まず少人数の健康なボランティアに対して医薬候補化合物を少量投与し、体内での吸収・分布・排泄などの様子(薬物動態)を調べる試験がおこなわれます。これを第Ⅰ相試験と呼びます。場合により、ごく少量(薬理作用がみられる量の100分の1程度)の治験薬を健康な人に投与し、薬物動態を調べることもあります。これを「第0相試験」という言い方をします。
・ 第Ⅱ相試験
第Ⅱ相試験では、いよいよ患者さんを対象とした試験がおこなわれます。比較的少人数の患者さんに対し、第I相試験の結果から安全と考えられる量の治験薬を投与します。これによって治験薬の有効性と安全性について調べ、どのような投与方法及び投与量が有効かを決定します。
・ 第Ⅲ相試験
最後の第Ⅲ相試験では、多数の患者さんを対象として、治験薬の有効性と安全性を試験します。すでに市販されている医薬またはプラセボ(本物とそっくりに作られた偽薬)を投与した患者さんと比較し、十分な薬効と安全性を示すかどうか確認します。これらの段階のどこかで、医薬として見込みがないと判断されれば、試験は容赦なく中止となります。
臨床試験は、開始前にまず詳細な試験計画を国に提出し、その審査をパスしなければなりません。また、臨床試験に参加する患者さんの権利を守るために、GCP(Good Clinical Practice)と呼ばれる基準が定められており、これに反した場合処罰を受けることとなっています。
こうして得られたデータは、都合の悪い結果を隠すことのないよう、失敗した実験のものまで含めて一切を厚生労働省に提出し、厳正な審査を受けます。この書類は、トラック一台分といわれるほど膨大なものになり、このため審査にも年単位の時間がかかることが普通です。こうして承認を得たものだけが、医薬として世に出ることになります。
これからの創薬研究の行方は
というわけで、恐ろしいほどに手間暇がかかるのが現代の臨床試験であり、細部に至るまで緻密さと慎重さが求められます。患者さんの健康、医療への信頼、そして巨額の利益がかかっているだけに、あらゆる面で不正の入り込む余地がないよう物事を運ぶ必要があるのです。
製薬会社の立場からすれば、どのような臨床試験をおこなえば他の薬との差を示すことができ、承認を得られやすいかの戦略を練ることが重要です。たとえばインフルエンザ治療薬では、患者さんが鼻をかんだティッシュペーパーを回収して鼻水の量を測定することで、回復具合を定量化しています。データの集め方や、治療の方向性をきちんと定めなければ、得られる承認も得られなくなります。
症例数を集めるための患者の確保、提出書類の作成、統計解析、厚生労働省や PMDA(医薬品医療機器総合機構、医薬品や医療機器の審査を行なう機関)との交渉など、開発部門の任務は多岐にわたります。各地の病院を回ってデータを集めるような人員も多く、基本的に研究所内だけで働く研究部門とは大きく業務内容が異なります。近年では、新薬は日本だけでなく世界各国での発売を目指すことが増えていますので、英語力を必要とする部門も多くなっています。
ということで今回はこれまで。創薬研究の難しさ、そしてその困難を乗り越えて医薬品が生み出されるやりがいまで感じていただけたらうれしく思います。次回は、研究職の働きかたなどについてもお伝えしたいと思います。質問やリクエストなどもお待ちしています。
※本記事は筆者個人の経験を基にしたものであり、運営元の意見を代表するものではありません。
次の記事はこちら:
研究職としての適性、キャリアを知る 『医薬品クライシス』著者・佐藤健太郎氏が語る、医薬研究職の世界 Vol.5
前の記事はこちら:
創薬研究の過程、その長い道のりとは 『医薬品クライシス』著者・佐藤健太郎氏が語る、医薬研究職の世界 Vol.3