人類最後の敵・がんに挑む ~体内にあった最強の武器(1)|世界史を変えた医薬の力

Contents
佐藤健太郎さんがサイエンスシフトのために書き下ろしたweb版連載「世界史を変えた薬」を掲載します。
今回は三大疾病の一つである「がん」の治療薬についてです。
◆
歴史を変えなかった病気
書籍版「世界史を変えた薬」では、梅毒・マラリア・壊血病・エイズなど、世界史を揺るがした疾患を取り上げ、それらの治療薬開発の過程と、その後の歴史を変えていった有様を描いた。だが読み終えた方は、「なぜあの病気が取り上げられていないのだろう」と思う疾患が、いくつかあったのではないかと思う。おそらくその筆頭は、がんだったのではないだろうか。
がんの治療薬を取り上げなかった理由のひとつは、世界の歴史に及ぼしたがんの影響が、各種感染症などに比べると大きくないことだ。今でこそがんは、日本人の2人に1人がかかり、3人に1人が亡くなる病気だ。しかし明治以前には、がんで世を去ったと断定できる人物は驚くほど少ない。たとえば戦国武将では、伊達政宗が食道がん、徳川家康が胃がんという説がある程度だ。
これは、がんが体内奥深くに発生する病気であるため、外観からはがんであると特定しにくいのが原因のひとつだ。そしてもうひとつ、かつてのがんの発生率はかなり低かったためでもある。がんは、様々な遺伝子の変異が積み重なって起きる病気であり、このためがん細胞が出来上がるまでには長い時間がかかる。がんが若年層に少なく、高齢者に多いのはこのためだ。先に挙げた政宗は68歳、家康は75歳で亡くなっており、当時としてはかなりの長寿の部類に属する。要するに19世紀以前の人々は、ほとんどががんにかかる前に他の病気で亡くなっていたというのが真相だ。
そして書籍でがん治療薬を取り上げなかったもうひとつの理由は、歴史を変えるほどのがん治療薬はまだ出現していない、と筆者は感じていたからだ。何しろ、がんは難しい病気だ。細菌の感染症なら、人間の細胞には影響せず、細菌の細胞だけを見分けて叩く薬を作ればよい。だががん細胞は、変異を起こしているとはいえ結局自分自身の細胞だ。これを見分けて攻撃するのは、極めて難しいことだ。
古典的な抗がん剤の仕組みは、DNAを切断するなどしてがん細胞の増殖を阻む、あるいはアポトーシス(細胞の自殺)を引き起こすというものだ。ただしこれら古典的抗がん剤は、正常細胞にも見境なく攻撃をかけてしまう。このため体へのダメージも大きく、脱毛や嘔吐などの辛い副作用も避けられない。
だが近年、各方面の進歩により、ようやくがん細胞だけを狙い撃ちにできる医薬が登場して、この世界が大きく変わりつつある。そこで今回は、近い将来に歴史を変えることになるであろう、新しいがん治療薬について書いてみよう。
抗体の発見

その新薬が見つかった場所は、地中深くの細菌でも、化学者のフラスコの中でもなく、我々自身の体内だ。その存在を世界で初めて示した男の名は北里柴三郎――2024年から、新千円札の顔となる予定の人物だ。
1885年にドイツへ渡り、時の細菌学の第一人者であるロベルト・コッホのもとに留学した北里は、その鋭い観察眼と卓越した実験技術で、たちまち頭角を現す。不可能と言われていた破傷風菌の純粋培養を成し遂げて世界を驚かせた北里は、返す刀で破傷風の治療法開発に乗り出す。
彼はまず、破傷風の症状を起こすのに、破傷風菌自体は必要ないことを突き止めた。破傷風菌は毒素を体外に放出しており、これが全身に広がることで症状を引き起こすのだ。では、どうすれば症状の発生を抑えることができるだろうか?ここで北里の発想は飛躍した。麻薬の一種であるコカインは、少量ずつ摂取して体が慣れていくと、普通の人なら死に至るような量を摂取しても中毒を起こさなくなる。これと似た現象が、破傷風毒素でも起こるのではないかと考えたのだ。
この予測はズバリ当たった。実験用のマウスに少量ずつ破傷風毒素を注射し、少しずつ量を増やしながら反復投与を行なった。そしてこのマウスに、一気に致死量となる毒素を注射しても、症状は起きなかった。コカインの場合同様、毒素に対する「慣れ」が生じたのだ。
では、この「慣れ」の正体は何だろうか。北里は、毒素を中和する何らかの物質(北里はこれを「抗毒素」と呼んだ)が、動物の体内にできるのではないかという仮説を立てた。探索の結果、抗毒素は血清に存在することを彼は突き止める。毒素に耐性ができたマウスの血清を破傷風毒素と混ぜ、健康なマウスに注射しても、破傷風の症状は起きなかったのだ。血清療法の完成であり、ここに医学史上の巨人として北里柴三郎の名が刻まれることとなったのだ。
これは、現代でいう「免疫」の力によるものだ。もちろん、一度かかった病気に二度とかからなくなるケースがあるのは、古くから経験的に知られていた。また18世紀末には、イギリスの医師エドワード・ジェンナーが、牛痘(牛がかかる感染症)の膿を注射することで、天然痘への感染を防げることを示している。ただし北里は、単に病気を防いだだけでなく、免疫現象が特定の物質によるものであることを学問的に示して見せた。ここに、北里を近代免疫学の祖と位置づける理由がある。
北里にはノーベル賞の候補にも挙がったが、受賞は成らなかった。第1回のノーベル生理学・医学賞は、北里との共同研究でジフテリアの血清療法を開発した、エミール・ベーリングが獲得してしまったのだ。基本となるアイディアを出し、手法を固めた北里が受賞を逸したのは不可解にも思えるが、ひとつにはジフテリアの方が社会的に重要な病気であったこと、またドイツ帝国を挙げた全面的バックアップがあったことが大きかったといわれる。現代の基準であれば、少なくとも北里は共同受賞を果たしていたことだろう。
抗体から医薬までの遠い道
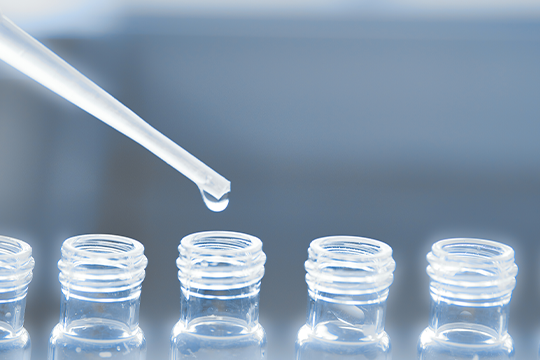
北里の「抗毒素」は、やがて「抗体」と呼ばれるようになり、研究が進むにつれてさまざまなことが判明してきた。たとえば破傷風菌の抗体は、他の病原菌に対しては無力であり、逆もまたしかりであった。また、血清療法は破傷風の予防・治療両面に大きな効果を挙げたが、問題もあった。場合により副作用が出ること、また投与を繰り返すと効果が下がってくることなどだ。
20世紀後半に入ると、抗体の具体的な構造が解明され始める。抗体の正体は、免疫グロブリンと呼ばれる、Y字型をしたタンパク質であった。このYの字の先端は「可変領域」と呼ばれ、侵入者に対して強く結合するものがすぐさま作り出される。数多のタンパク質からターゲットだけを完全に認識する「特異性」は、抗体の重要な特徴だ。
生体に危険を及ぼすタンパク質に強く結合し、取り押さえてしまう抗体の力は、うまく活用できれば治療法として無限の可能性を持つ。だが、その取り扱いはなかなか難しい。たとえば先ほど、血清療法は繰り返すと効果が落ちると書いた。これは、ウマ血清中に含まれる抗体もまた体外から来たタンパク質であるため、「抗体の抗体」ができて働きを抑えてしまうのだ。効き目が落ちるくらいならまだいいが、アナフィラキシーショックのような重篤な症状を引き起こすこともありうる。
この、強力だが諸刃の剣でもある抗体を、いかに人類は飼い慣らしていったか、そしてがんの治療薬へと展開していったか――このあたりは、また次回で述べていくとしよう。
※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。
◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐藤健太郎さんのweb版連載「世界史を変えた薬」








