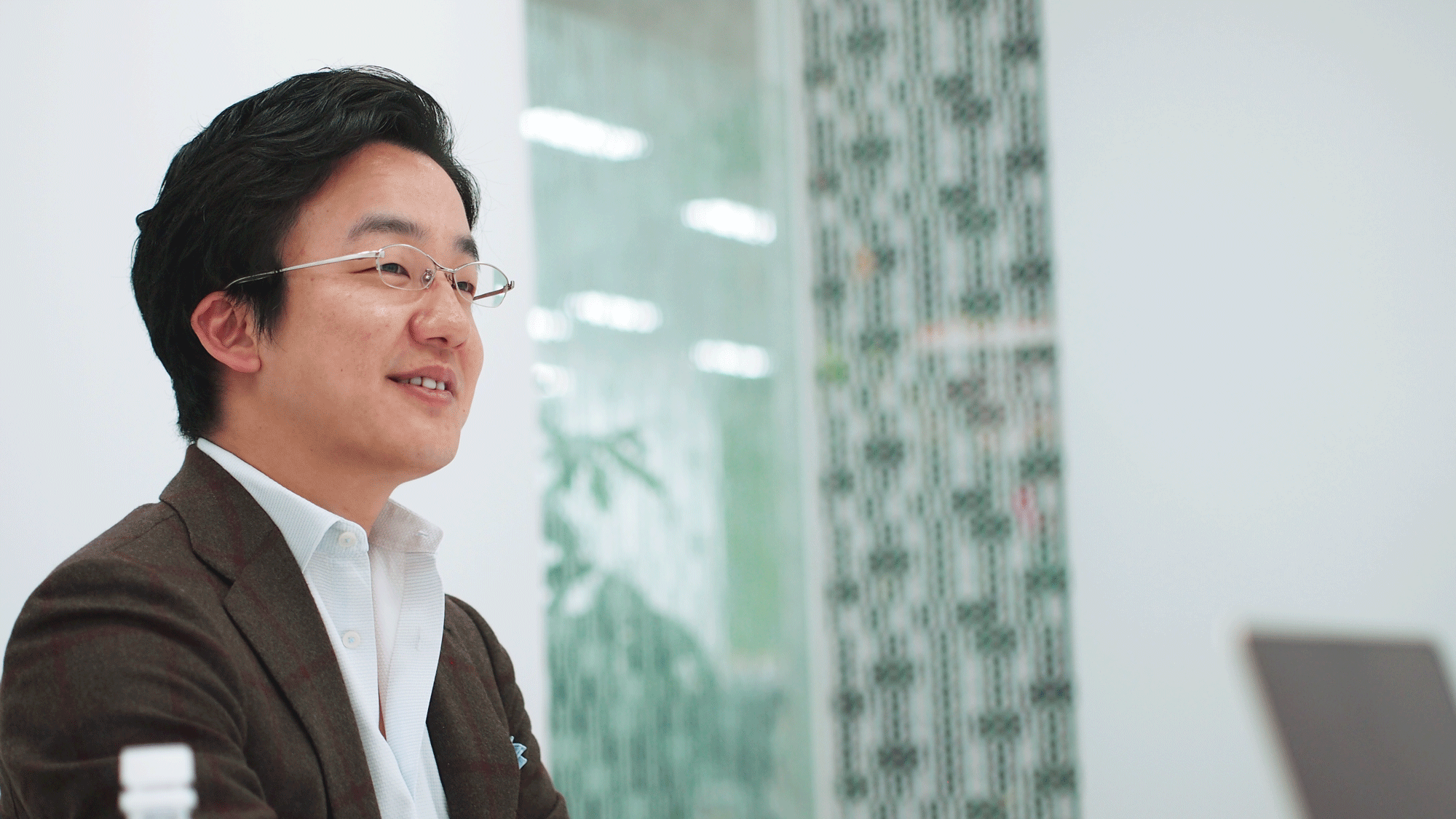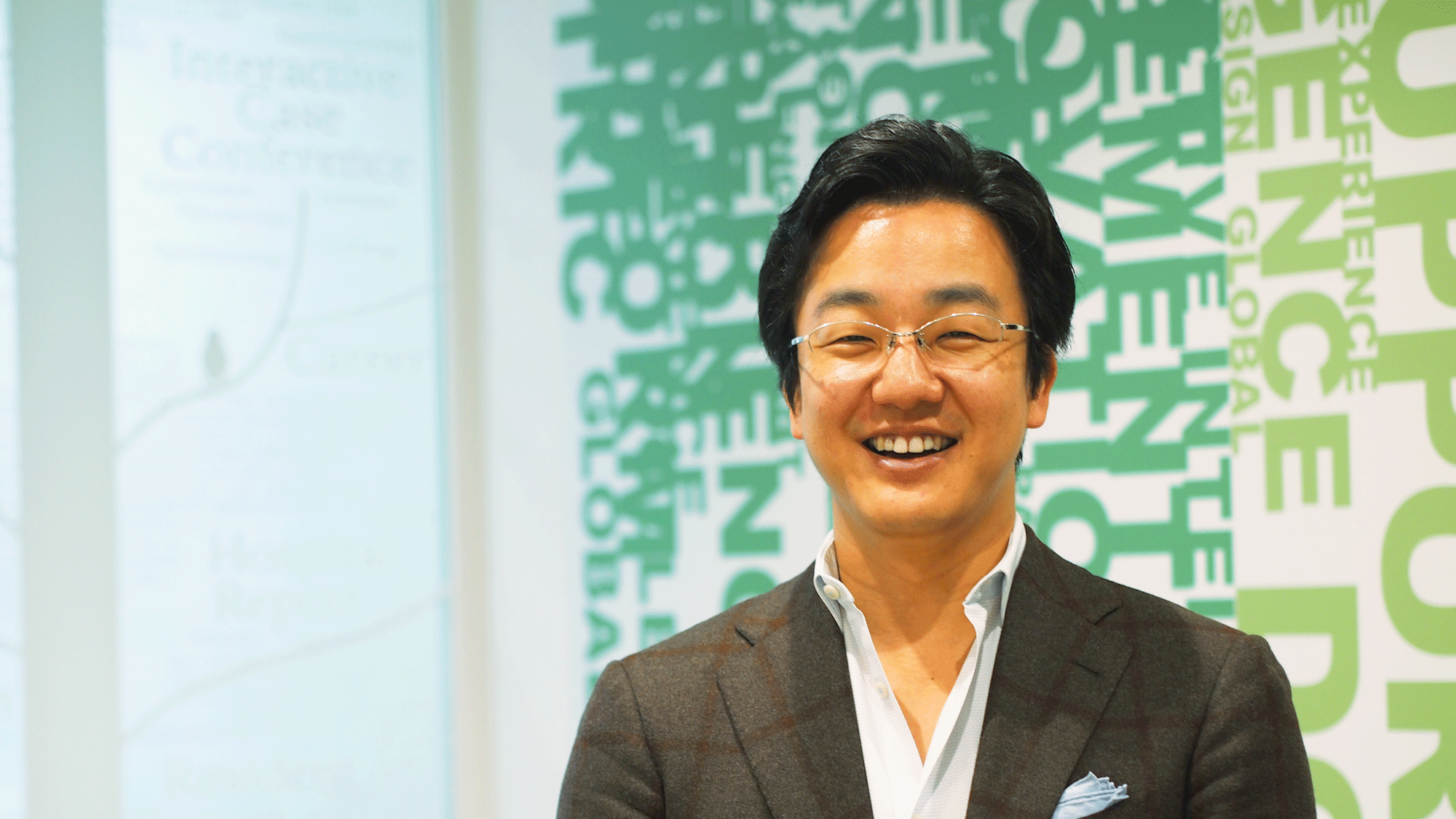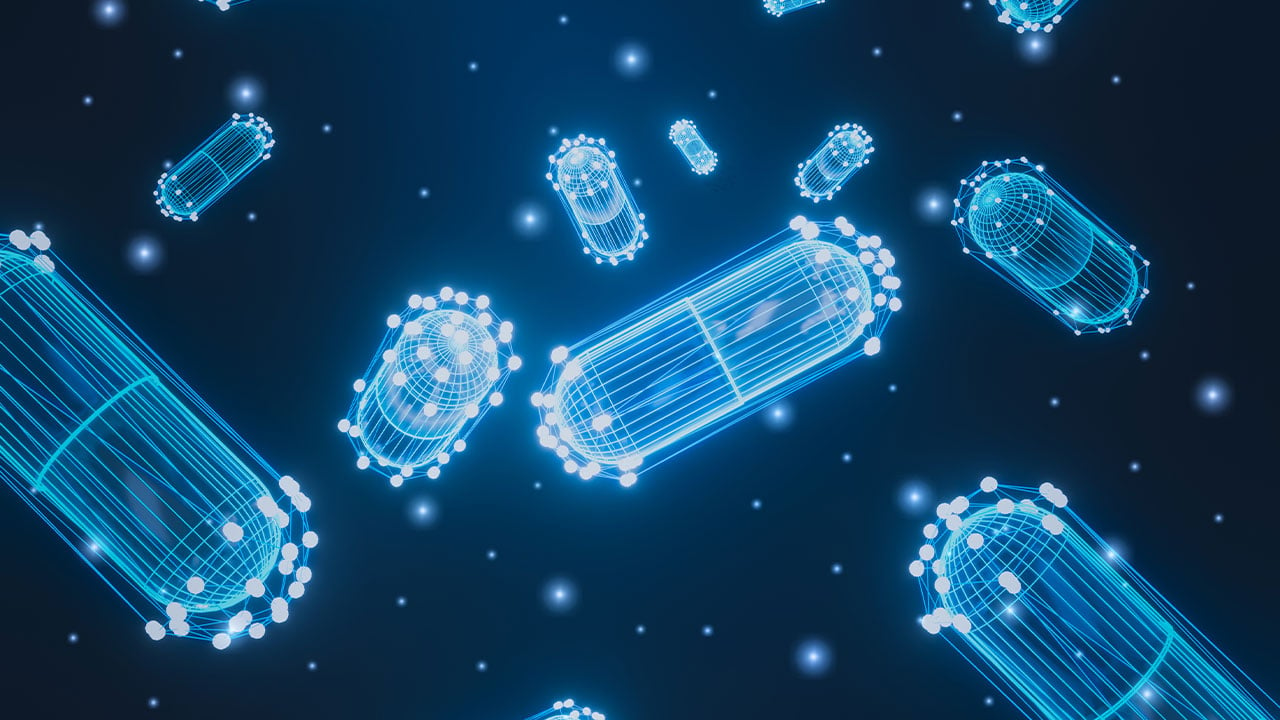メタデータ・野村直之氏に聞く “AI・人工知能時代の働き方” 後編

Contents
AIはすでに私たちの暮らす社会に大きなインパクトを与えています。とはいえ、本当にAIは人間の脅威となるのか。仕事の現場ではどういう影響をもたらしているのか。そういった疑問にはっきりと応えてくれる記事は多くありません。
今回は30年以上、人工知能研究に携わってきた第一人者であり、「人工知能が変える仕事の未来」(日本経済新聞社)という著書を出版されたばかりのメタデータ株式会社の代表・野村直之さんにお話をうかがいました。テーマは「AIによって、これからの社会や働き方がどう変化していくのか、そして私たちは、どう働いていくべきなのか」。後編では「AIが浸透する社会で、どう働いていくべきか?」について語っていただきます。
メタデータ・野村直之さんに聞く “AI・人工知能時代の働き方” 前編
AIによって変化する仕事 人はどう変わるべきか
━━AIの浸透によって、働き方はどう変わるのでしょうか?
業務プロセスのごく一部、平均的に数パーセントがAIに置き換わっていくと考えています。その変化は脅威に感じるようなものではなく、インターネットの普及で業務プロセスが変わっていった流れと大きな違いはありません。気がつくと、「弱いAI」¹が人々の仕事の煩雑な部分を引き受けてくれている……、そんなイメージです。
¹ AIの「強弱」について、前編ご参照
例えば、世の中にはエンジンの音を聞いただけで、その種類が分かるというベテランのエンジニアがいます。経験を積んだ一握りの人だけが手に入れられる専門性です。しかし、米国の企業OtoSenseが開発した音声認識AIのシステムは、すでに人間のベテランエンジニアの能力を上回る1000種類のエンジン音を聞き分け、認識することができます。このように専門性に特化して、大量のデータを高速に認識し、振り分けるような仕事に関しては、AIが人間に優っているのです。
とはいえ、AIは与えられた情報を認識することはできますが、概念そのものを獲得しているわけではありません。3歳の子供に「ママ」と「鳥」と「海」の写真を見せて、「どれがママ?」と聞けば100%正答するでしょう。しかし、AIに学習させた後で3つの画像を見せても「ママ:95%、鳥:4%、海:1%」といった答えしか出せません。主体性を持って、対象に意味づけや価値づけをすることはできないのです。
先ほどのエンジンの音で言えば、AIはエンジン音でエンジンの種類を聞き分けることはできても、ベテランエンジニアが音から感じ取る「エンジンの調子の良さ、悪さ」を判断することはできません。こうした知識に基づき、判断力や理解力を発揮する「結晶性知能」と呼ばれる能力は、65歳でピークを迎えるといわれます。また、新しいスキルを獲得する能力も50歳代後半まで伸びるそうです。80歳のおばあちゃんでも、孫とメールをしたいという動機があれば、パソコンやスマホの使い方を覚えます。そんなふうに自らのモチベーションによって能力を伸ばし、学校の先生のように他人のモチベーションに働きかけて新たな能力を伸ばすということはAIにはできないことです。
学習した知識を加工、応用して新しい知識を生み出すことは人間にしかできません。つまり、今後は人間が得意なこと、AIが優位なことを業務ごとに分け、助け合う形となっていくはずです。例えば、AIが大量のデータにマッチングをかけて、これまでは発見できなかった有望な見込み顧客を探し、営業マンがアプローチしていく。担当者はマーケティング能力や、顧客の新しい要求を発見する感性を磨くことで価値を高めることができます。
━━AIは「研究」という仕事に、どのような影響があるでしょうか?
研究の分野に限らず、AIはテキスト、音声、画像といった従来型の情報システムが扱いにくかったメディア、コンテンツを認識し、検索、分類、要約、データ表現の変換(テキストから画像、図表など)の場面で活躍してくれることが期待できます。
しかも、AIは365日24時間、寝ることもなく疲れもせず、社内のデータベース、社外のWeb上の情報などを大量に探索します。そういったAIの特性は、研究者が必要としている知識をまとめる助けとなり、直面している問題の解決に役立ってくれるはずです。
しかし、人間の情報認知能力や表現能力、発信能力が突然進化するわけではありません。ですから、情報量や質を、受け手や発信者である人間の処理容量、様態に合わせて変換するAI的なソフトウェアも登場してくることでしょう。いずれにしろ、AIは人間の知的生産プロセスを支援する道具として発展していきます。
そうなったとき、当然、研究者も変わっていく必要があります。
例えば、学生の中には「英語が苦手だから、理系に行く」という間違った選択をする人がいます。あるいは「人との関わりが苦手だから、研究の世界に」という人もいます。どちらのタイプも将来を見据えた場合、研究者として力を発揮することはできません。大学、企業問わず、海外で活躍している研究者に共通するのは、営業能力とプレゼン能力を併せ持っている点です。そして、自分の実績をきちんと表明する自己アピール力。これがなければ、欧米、インド、中国の研究所では研究費を確保することができません。また、本人のボーナスを含めた給与、待遇、権限を増やすためにも営業能力、プレゼン能力が欠かせない現実があります。
AIが知的生産プロセスを支援してくれる分、研究者にはAIと差別化できる能力が求められます。人と人とのつながりの中で、研究の意味や価値をアピールし、成果につなげられること。それが営業能力であり、プレゼン能力です。
人としての創造性を引き出すこと
━━AIの発展した社会で活躍するためには、どのような分野で強みを磨けば良いのでしょうか?
今後、もしAIのせいで失業者が増えるとすれば、生産性が1年で10倍などありえない速度で向上したか、人間をできそこないの機械のように使っていた職場においては、AIを使いこなせない人材や、クリエイティブな非定常的な業務にシフトできない人材が多かったからと言えるでしょう。そのような人材を生み出した要因の多くは、初等中等教育、職業訓練、職場での業務経験において、ひたすら一定の作業に「慣れさせる教育」を施すという間違ったシステムのせいではないかと考えます。
本質を理解し、あるいは逆に無用の理解を自らスキップして、ブラックボックスはありのまま受け入れ、機転を利かせてその場の判断で知識やさまざまなAIを取捨選択し、「良い加減に」動ける人材を育成するべきです。
なぜなら、一定のパターンを覚え込むような教育、勉強ではAIに勝てないからです。そのためにも文系学部を、特に社会科学系より人文科学系、そして芸術系の学部こそ育成し、振興しなければならないでしょう。自然科学、工学系でもAIのできそこないのようにゆっくり不正確な計算をする人材ではなく、大局観を持ち、上司や組織のリーダーの予測もつかない提案を出し、ビジョンを描き、あとからじっくりそれが理解されるようなミニ天才を多数輩出すべく、創造性を引き出す教育に大きくかじを切るべきでしょう。
そして、初等中等教育の場では、ひたすら従順に単純作業に従事するだけのワーカーを作り出すような発想、仕組みを根絶すべきです。そうやって育成された人材は、将来、AIに負けてしまいかねないからです。機械的な演習、「ドリル」を反復させるような教育法では、その生徒は精度もスピードもAIに負ける存在になってしまいかねません。
また、そのような教育を受けてきてしまった人は、そこから脱することです。そのための方法は、「なぜ?」と問うこと。仕事について「なぜこれをやるべきなのか?」と考えることは人間にしかできない能力です。前編でもお話ししたとおり、自発的、自律的に働こうという意志を持ったAIを作れる見込みは立っていません。
「なぜ?」と問い、自発的に問題を発見し、それを解決するために自律的に枠組みを考え、自分の責任で粘り強く試行錯誤すること。こうした取り組みを学生時代の趣味や創造的なアルバイトのなかで繰り返すことが、人間にしかできない仕事を担う能力を鍛えてくれます。
逆に、自分の専門とする領域だけにこだわり、単純作業に逃げ込むように没頭するといった時間の使い方は、それこそAIに負けてしまう自殺行為です。薄く広く物事を知っているだけではなく、領域をまたいで深く幅広い教養を身につけていくこと。そのためにはやはり、「なぜだろう?」と問い、考えていく必要があります。
なぜなら、「なぜ?」と考え続けることで、私たちは縦横無尽に違う分野へと目を向け、その問いへの答えを見つけようとしていくからです。その姿勢こそ、いつの時代にも研究者に必要不可欠な素養なのです。