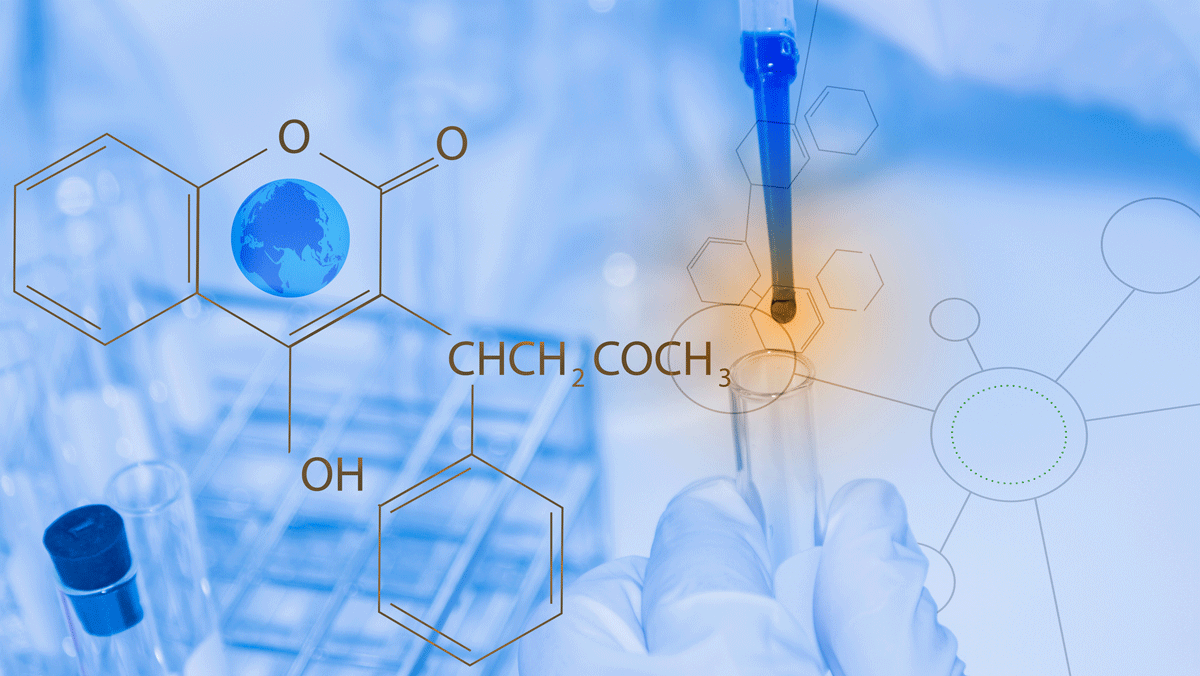「その名は「H2ブロッカー」〜病気を治すロジックの誕生|世界を変えた医薬の力・前編」

サイエンスライターとして、医薬や化学を専門の題材とし、著述活動を続ける佐藤健太郎さん。このサイトの読者のみなさんも、よくご存じでしょう。
先日のお勧め本に続き、今回のテーマは、医薬品について。言うまでもなく、佐藤さんのかつての「本業」です。
◆
筆者はこれまで、医薬に関する本を数冊著してきた。そのたびごとに、ビジネスの面、科学の面、経済の面など様々な角度から、医薬という不思議な製品を捉え直そうとしてきた。しかしその奥は恐ろしく深く、到底描ききれたという実感はない。
2015年に講談社現代新書から刊行した「世界史を変えた薬」は、そうした中の一冊だ。清の名君・康熙帝の命を救ったキニーネ、現代まで尾を引くアヘン戦争を引き起こしたモルヒネ、不治の難病と思われたエイズの治療薬アジドチミジンなど、文字通り世界の歴史を大きく揺り動かしたいくつかの医薬を取り上げ、紹介した書籍だ。
幸いにして同書は好評をいただいたが、内容についてはやや心残りもあった。ひとつには、歴史的な部分を意識するあまり、第二次世界大戦以降の医薬についてはほとんど取り上げられなかった点だ。いうまでもなく、この期間にこそ重要な医薬は数多く登場している。歴史の流れに大きく関与したもの、「あの時代にこの薬があれば」と思うものも、当然少なくない。
そうしたところに、本サイトにて「世界史を変えた薬」の続きを書いてみてはというご提案をいただいた。筆者として願ってもない話であり、書籍に収録できなかったテーマをこちらで書かせていただくこととした。まずは、胃潰瘍をめぐる医薬の物語を取り上げてみたい。
ストレスの誕生

現代を生きる成人であれば、誰しもストレスを経験するだろう。人間関係、満員電車、仕事のノルマ、指導者や上司からのプレッシャーなど、今の社会はストレスの元には事欠かない。
生理学者ハンス・セリエによって、ストレスという言葉が初めて使われたのは1936年、一般向けの著書によって広く知られるようになったのは1956年のことだ。ストレスとは、非常に現代的な概念ということになる。
ストレスはさまざまな疾患の原因あるいは増悪因子となるが、最もよく知られている直接的な影響は、胃潰瘍による胃痛だろう。2019年に現役を引退した、元メジャーリーガーのイチロー選手は、28年にも及んだ現役生活の中でほとんど長期離脱することがなかったが、2009年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の直後には胃潰瘍によって8試合を欠場している。あれほどまでに体調管理を徹底し、多くの逆境を経験してきたイチローにとってさえ、世界大会のプレッシャーはあまりに過酷であったのだ。
しかし、ストレスによる胃潰瘍は、何も近代になって初めて現れたものではない。古代においても、アレクサンダー大王の猛攻にさらされたギリシャ将兵に、吐血者が続出したとの伝承がある。中国の説話においても、親族の死や不当な処分にさらされた人が悲憤慷慨し、血を吐いたという描写は数多くあり、これらは胃潰瘍によるものである可能性が高い。
芸術家もまた、多大なストレスと向き合わねばならない職業だ。近代日本を代表する画家・岸田劉生(1891-1929)は胃潰瘍のために38歳で世を去った。また、永井荷風(1879-1959)、室生犀星(1889-1962)、横光利一(1898-1947)、芥川龍之介(1892-1927)など胃潰瘍に苦しんだ作家は多く、いわば文人につきものというべき病気であった。
中でも最も有名なケースは、やはり夏目漱石(1867-1916)の胃潰瘍だろう。漱石は43歳の時に療養で訪れていた伊豆の修善寺で大量に吐血し、生死の境をさまよった。その後も不調を抱え続けた漱石は、ついに大正5年に胃潰瘍からの大量出血によって世を去っている。
作家・山田風太郎はその著書「人間臨終図鑑」で、漱石が今しばらく生き長らえていれば、小説「明暗」が彼の最高傑作として完結していただろうとし、「これこそあと少し命をやりたかった最大の人」と嘆いている。時に漱石49歳、現代ならばこれから脂が乗ってくるといわれる時期だろう。
このように、ほんの百年前には、胃潰瘍は間違いなく生死を左右する病気であった。だが現代を生きる我々からすれば、胃潰瘍は「ちょっと胃が痛む」程度のことで、命にかかわるような大病のイメージではない。かくも大きく胃潰瘍のイメージが変わったのは、ひとつの医薬の登場が契機であった。
胃潰瘍とは何か

胃は、いうまでもなく食物の消化を担当する臓器だ。胃液はpH1.5程度の強酸である上、ペプシンなどの消化酵素をたっぷり含んでいるから、効率よく食肉などのタンパク質を分解できる。美味しい食事は、胃の中で3時間もすればどろどろの液体に変わってしまうし、鉄さえも胃液にかかれば泡を吹き上げて溶けてしまう。
だが考えてみれば、胃袋自身もタンパク質でできているのだから、胃液で消化されてしまうはずだ。こうならないのは、胃の上皮細胞から分泌される粘液や炭酸水素イオンによって、胃が保護されているためだ。しかしストレスなどによって交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、胃酸が一気に分泌され、胃壁を消化してしまう。これが胃潰瘍の正体だ。
古代ギリシャでは、貝殻をすり潰した粉末が、胃潰瘍の治療に用いられたという。貝殻の主成分はアルカリ性の炭酸カルシウムだから、これによって胃酸を中和できるわけで、理にかなった方法だ。現在でも、軽度の胃潰瘍や胸焼けに、酸化マグネシウムや水酸化アルミニウムなどの制酸剤は広く用いられる。
しかし制酸剤にできることは限界があり、重度の胃潰瘍は外科手術によって切除する他なかった。なんとか胃酸を制御できないものか――その鍵として浮かび上がってきたのは、ヒスタミンという物質であった。
ヒスタミンは簡単な構造だが、血管の拡張や平滑筋の収縮など、多くの生理作用を持つ重要な物質だ。そしてヒスタミンには、胃酸分泌のスイッチを押すはたらきもある。ヒスタミンが胃の細胞にある「受容体」と呼ばれるタンパク質に対して結合することで、胃酸が放出されるのだ。ヒスタミンは鍵に、受容体は鍵穴にたとえることができる。
つまり、何らかの化合物で受容体の「鍵穴」をふさいでしまえば、ヒスタミンの作用は封じられ、胃酸の放出が抑えられると考えられる。これは重要なアイディアだったが、現実にはうまく行かなかった。
実は、1940年代にはすでに、ヒスタミンの鍵穴をふさぐ物質(「拮抗剤」という)は見つかってきていた。しかしこれらには、アレルギー反応を抑える力はあったものの、どういうわけか胃酸分泌はさっぱり抑えなかったのだ。当時の生化学は、この謎を解くにはあまりに力不足であった。一方で、1960年代にはガストリンという新たな胃酸放出因子が見つかり、こちらの方が研究者の注目を集めるようになっていた。
だが、やはりヒスタミンこそが胃潰瘍を抑える鍵であり、その謎を解くことに集中すべきと考える人物もいた。イギリスのスミスクライン&フレンチ社(現グラクソ・スミスクライン)に所属した薬理学者である、ジェームス・ブラックがその人だ。彼の謎解きと、画期的新薬開発の物語は、次回に詳しく記すとしよう。
※本記事の内容は筆者個人の知識と経験に基づくものであり、運営元の意見を代表するものではありません。
◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐藤健太郎さんのweb版連載「世界史を変えた薬」
その名は「H2ブロッカー」〜病気を治すロジックの誕生・後編
人類最後の敵・がんに挑む ~体内にあった最強の武器(1)
人類最後の敵・がんに挑む ~体内にあった最強の武器(2)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー