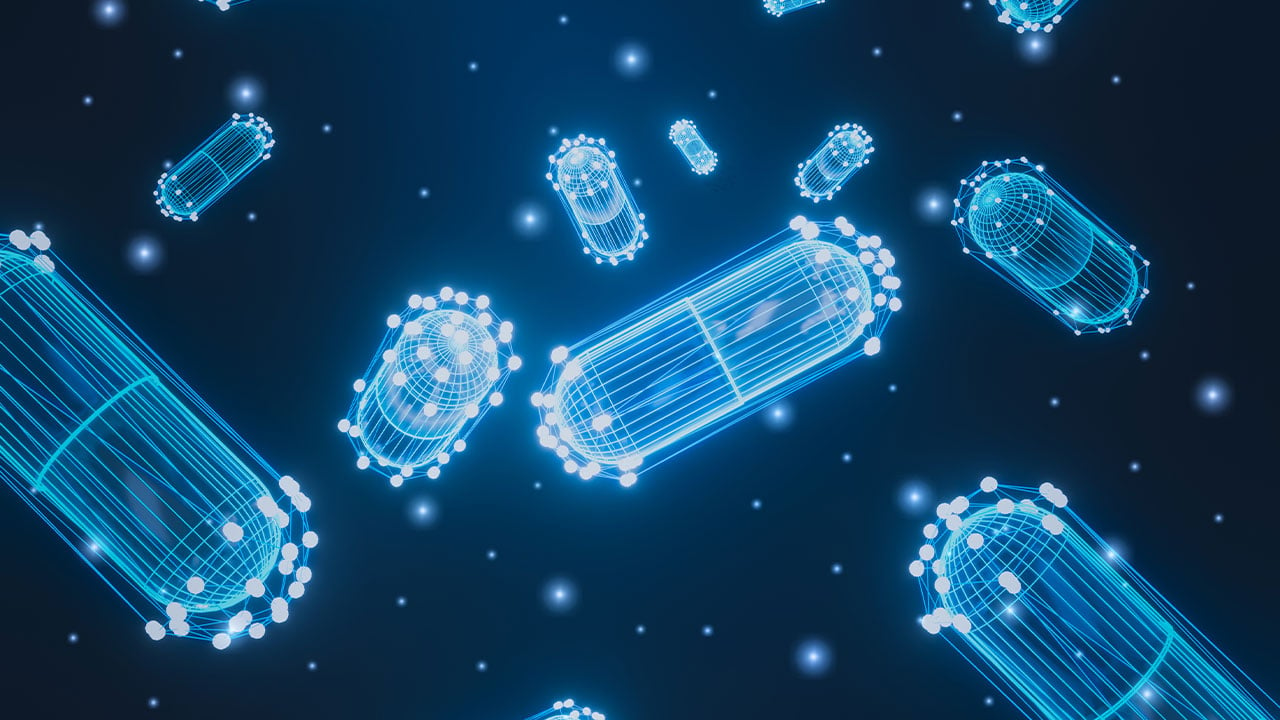海の中から新しい薬品資源を見つけ出す。|SDGsに取り組む北海道大学大学院 薬学研究院の挑戦【後編】

前回の記事はこちら
海の中から新しい薬品資源を見つけ出す。|SDGsに取り組む北海道大学大学院 薬学研究院の挑戦【前編】

取材協力:
北海道大学 大学院薬学研究院 教授
脇本 敏幸さん
東京大学大学院農学生命科学研究科出身。海洋生物活性天然物の探索に関する研究を専門としている。
◆
なぜウミウシが海綿を食べるのか?「地球環境への関心」

「高校生の頃から生態学やエコロジーに興味があって、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』など環境問題を取り上げた本に感銘を受けていました。それで大学では、環境保全分野の研究をしようと考えたのです。ところが今の若い人には想像できないと思いますが、私が高校生だった90年代初頭は、日本の大学で『環境』と名がつく学部を持っているところはほとんどありませんでした。」
「水産についての授業で、『海の中の生き物は、物質を交換することによってコミュニケーションしている』という話を聞いたのが、この研究の道に進む最初のきっかけでした。『ケミカルコミュニケーション』と呼ばれますが、海の生き物の多くは毒や防御のための低分子物質を体内で作り、それを放出して、食べさせることで天敵をやっつけたり、フェロモンとして出すことで仲間を集めたりしています。目に見えない大きさの物質による生物同士のコミュニケーションが、種を超えて生態系を作っていることが、とても面白く感じた。それまで生物がそのようなやり取りをしているとはまったく知らなかったので、『生態系の保全を考えるなら、このことを学ぶ必要がある』と思ったのですね」
「海綿動物の多くは他の生物にとっての毒となる化学防御物質を作っているため、海綿を食べる生物は海洋中にほとんどいません。しかしウミウシは、海綿を食べるのです。ウミウシも面白い生き物で、もともとは巻き貝の仲間ですが、進化のなかで貝殻を捨てて、生身で生きています。柔らかいのですぐに魚などに食べられそうですが、海綿の毒を生体濃縮して自分の体に溜め込んでいるので、魚も食べないのです。ウミウシは岩に花びらのような卵を産み付けますが、それにも毒が濃縮されているので、外敵からほとんど食べられません。」
「生き物が無駄にエネルギーを使って、趣味で物質を合成するわけがないのです。しかし生態系のなかで、その物質がどんな意味を持っているのか、すぐにはわかりません。人類は、海洋の中で日々生き物たちが繰り広げているケミカルコミュニケーションの、ほんのごく一部しかまだ理解できていないのです。その意味を発見することが、僕らの仕事だと思っています。人間にとって薬になりうる物質が発見できれば一番いいですが、薬にならなくても、意味を見出すことが非常に面白い。そこにいちばん、この研究の魅力を感じますね。」
天然物化学に期待される「新しい抗生物質」と「抗がん剤」

「最近では、耐性菌に対する『最後の砦』と言われたバンコマイシンという薬にも、耐性を持つ菌が発見されています。新しい作用機序を持つ抗生物質の発見が、医療全体の喫緊の課題となっているのです。また抗がん剤も、これまで見つかったものの多くは天然物を原料としています。抗生物質と抗がん剤は、人工的に合成しにくい分野の薬なのです。最近では新しい構造や作用を有する抗生物質、抗がん剤の候補が見つかると、即座に『ネイチャー』『サイエンス』という一流の科学雑誌に論文が載ります。それぐらい、期待されているということです。」
「たとえばある植物から取れるマラリアによく効く薬があるのですが、その薬をグローバルマーケットに十分な量を提供するためには、とんでもない量の植物を育てる必要があります。植物を育てるには土地も肥料も必要ですし、農作業に人手もいるので、コスト的に見合わないのですね。マラリアという病気は主に熱帯地域の発展途上国で流行っているので、薬価が高くなる生産手法はとれません。有効成分を有機合成でつくる方法もあるのですが、その原料には石油が必要なので、やはり環境に大きな負荷がかかってしまう。しかし植物から成分を作る遺伝子をとってきて、酵母や大腸菌に組み込めば、一つの培養タンクで大量に生産することができます。製薬メーカーにとっても、その技術が実現できれば、とてつもない利益を生み出す可能性がある。実際にいま、欧米を中心に世界中の製薬メーカーが既存の抗がん剤などを酵母で作り出す研究を始めています。」
天然物の創薬は、製薬業界のSDGs推進にも役立つ

「海の生き物たちの間で行われるケミカルコミュニケーションを理解し、環境に負荷をなるべく与えないかたちで天然物を薬に用いるこの研究は、製薬業界のSDGs推進にも大きく役立つはずです」
脇本教授は2014年、伊豆沖に住む海綿から、「カリキュリンA」という細胞毒性物質を生み出すバクテリアを同定することに成功した。世界で初めてのその発見は学界でも高く評価され、化学と生物学に関するトップ科学誌として知られる「ネイチャーケミカルバイオロジー」に論文が掲載された。その研究がスタートしたのは2010年、実を結ぶまでには4年の歳月がかかった。取材の最後に「研究を進めるなかで、いつも念頭に置いていることはありますか」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「可能性が低くても、この先に何か『宝』があると信じられるのであれば、『やってみよう』と決断することです。実際にネイチャーケミカルバイオロジーに載った研究も、最初は上手くいくかどうかまったくわからなかった。海綿に医薬品候補物質を生み出すバクテリアがいることは、世界の研究者みんなが知っていましたが、10年かけても見つからない可能性は十分あった。そんなリスクの高い研究には、誰も取り組もうとしなかったのです。しかしだからこそ、自分がやる意味があると思えました。これからも多くの研究者が取り組んでいるテーマの中で競争するのではなく、自分だからこそアドバンテージがある研究に、挑んでいきたいと思っています。」