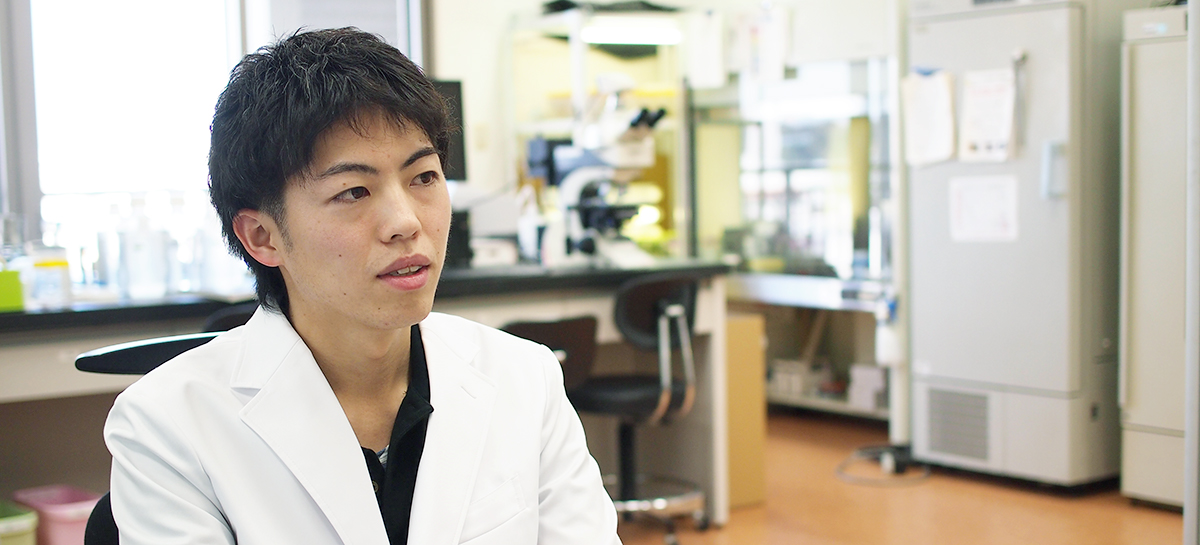「決して諦めない心」で、異分野を駆け抜ける━━社会を動かすイノベーターたちのプロジェクト Vol.5 株式会社PROVIGATE(後編)
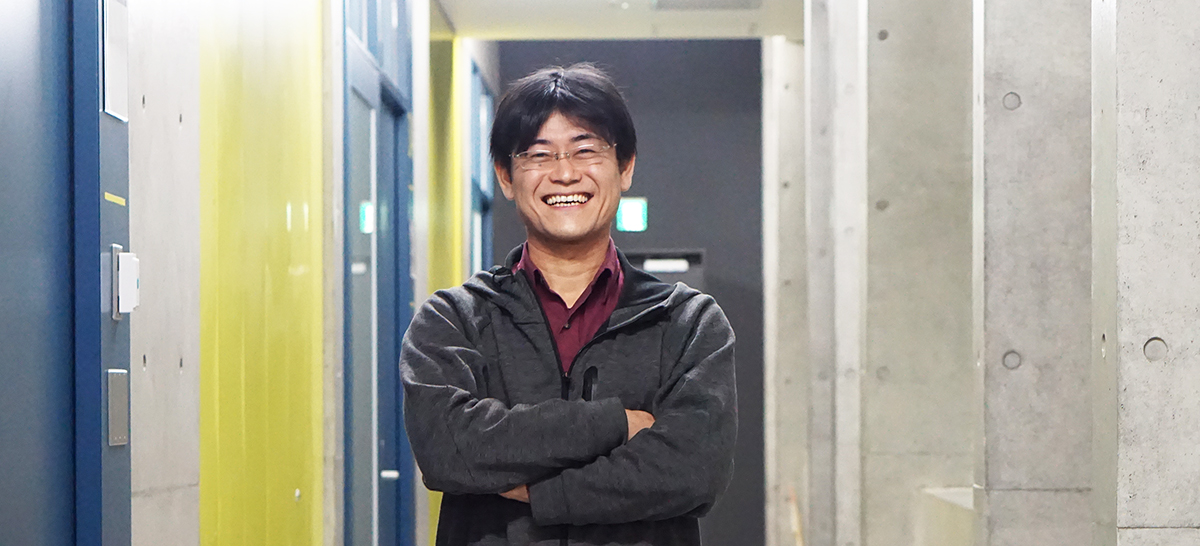
「涙で血糖値を測る」デバイスを開発している株式会社PROVIGATEで、最高研究開発研究者を務める加治佐さん。そのキャリアには、数々の「異分野への挑戦」があったという。どのようにキャリアを選択してきたのか、困難な道にどう向き合ってきたのか。研究者としてのルーツに迫ります。
◆
生物学から半導体の世界へ
東大発ベンチャーのPROVIGATEは、涙に含まれる糖(ブドウ糖、グルコース)の値を測る装置(グルコースセンサ)の開発に取り組んでいる。それは、同社の最高研究開発責任者・加治佐平(かじさ たいら)さんにうってつけの研究開発対象だったと言えるだろう。
この装置は、東京大学大学院工学系研究科の坂田利弥准教授が開発してきたバイオセンサの技術を応用している。検出すべきターゲットとなる生体分子を決め、それを精度よく捕捉できる「界面」を設計し、この「界面」を通じて、半導体デバイスが生体分子を定量的に検出できるようにする。

すなわち、この装置の開発には、生体分子に関する知識(生物学)と半導体デバイスに関する知識(工学)、そして両者をつなぐ「界面」の知識(化学)の、三つの分野を横断する幅広い知見が必要とされる。加治佐さんは、まさしくこの三つの分野を横断するキャリアを歩んできた。
最初に進んだ道は生物学だ。東京大学大学院農学系研究科で、キノコが植物の細胞壁をいかに分解するかの研究に取り組んでいた。
「細胞壁の主成分は、グルコースが多く連なってできるセルロースです。キノコがどのようにしてセルロースをグルコースに分解するかをひたすら研究していました。ゲノムや分子生物学の面白さにどっぷりはまり、ドクターまで5年間、研究に没頭していました」
加治佐さんのグルコースへの知見は、大学院生時代から蓄積してきたものなのだ。
2009年に博士課程を修了すると、加治佐さんはそこで方向転換をする。
「大学院では、セルロースがグルコースに分解する過程を研究していましたが、次第に、逆方向の反応にも興味が出てきました。低分子を組み合わせて新たな高分子をつくる。そんな研究に取り組んでみたくなって、大手化学メーカーの研究部門への就職を決めました」
その就職先で、意外な展開が待っていた。生物学の知見を生かせる部門への配属を想定していたが、配属されたのは、太陽光発電パネルに使う樹脂素材を開発する部門だった。
「当時は太陽光発電パネルの市場が大きく伸び始めた時期で、会社として新たなマーケットに参入するべく設立されたばかりの部門でした。ミッションは、太陽光発電素子の前面に張る樹脂の開発です。前面板にはガラスを使うのが主流でしたが、ガラスより壊れにくい樹脂で効率よく太陽光を吸収でき、発電素子との接合性が高い素材の開発が求められました」
発電素子は半導体デバイスだ。加治佐さんはこの仕事を通じて半導体に関する知識を身に着け、半導体と樹脂という異なる素材を接合する「界面」の技術を知ることになったのだ。
分野の壁を、いかにして越えるか
加治佐さんが就職して4年目に、その後の進路を変える運命の出会いがあった。
「『界面』の面白さに惹かれて研究を進めていくうち、坂田先生の研究を知る機会がありました。半導体デバイスで生体分子を検出する。それには『界面』の設計が重要だと。これぞまさしく自分にふさわしい研究ではないかと思っていたところに、研究室で公募が出たので迷わず応募しました」
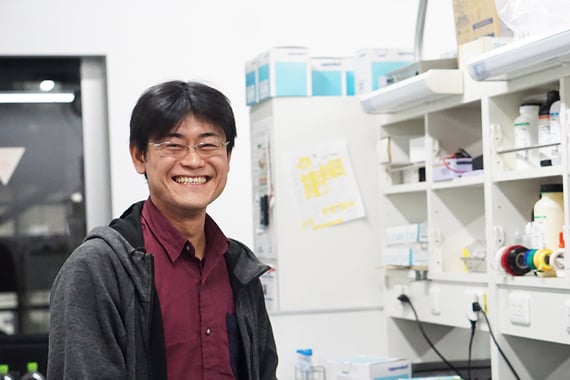
生物学の研究から化学メーカーへ。そこでは新たに半導体について学び、2013年に再び大学へ。それは、これまでのキャリアをひとつにつなげるための、新たな異分野への挑戦だった。その挑戦は少しずつ実を結び、2015年にはPROVIGATEを立ち上げた。そして2018年の今、開発を手掛けてきた装置はプロトタイプとして形が見えてきた。
異分野を渡り歩く――と、ひとくちに言うのは簡単だが、加治佐さんはどのように分野の垣根を越えてきたのだろうか。重要なのは、「異なる分野の共通点を見つけること」だと、加治佐さんは自身の経験を語った。
「大学院で研究していたのは、セルロースという高分子が、グルコースという低分子にいかに分解されるかです。就職してまったく違う分野に進んだと思われるかもしれませんが、私としては、やってきたことの見方を少し変えただけです。大学院での研究が、低分子から高分子を合成する際にもきっと役立つはずだと思っていました。就職先では、異なる素材を接合させる『界面』の技術の面白さや重要性に気づき、その延長で、坂田先生の研究室に飛び込みました。私の場合は、自ら望んで進む道を変えてきましたが、思いがかなわず異分野に進むことになった人も、それまでやってきたこととの共通点を見つけて、新しいことに没頭してみてほしいと思います」
加治佐さんは、こうも言う。
「少し前なら、研究者は“狭く深く”自分の専門分野を掘って極めていけばよかったのかもしれません。ただ、今では融合領域の研究が盛んに行われ、学問分野の垣根がなくなりつつあります。自分の専門分野で強みを持っているだけではなくて、異分野についてもある程度の知見がないと、新たなことを産み出すのが難しくなっています。浅くてもいいから広い分野の知識を持ち、深掘りする分野をできれば複数持つ。“T型1”もしくは“Π(パイ)型2”と呼ばれる人材が、さまざまな分野で求められるようになっています」
1T型人材:縦に1つの専門性を掘り下げる「I型人材」に対し、1つの専門性に加えて、横に広がる幅広い知識をもつ人材のこと。イノベーションを生むために、専門分野のみでなく幅広い知識を持っていることが必要、という考え方から求められている。
2Π(パイ)型人材:幅広い知識を持ちながら、2つの専門性を掘り下げる人材のこと。2つの専門性を併せ持つことで希少性が高く、それらを融合させて新しいものを創造できることが期待される。
東大野球部で培った、「決して諦めない心」
新たなことへの挑戦には失敗がつきものだが、加治佐さんは「失敗すらも楽しい。課題が大好きです」と笑顔で語る。
「いま開発しているグルコースセンサも、失敗や課題の連続でした。それをひとつずつ乗り越えて、ようやくプロトタイプにまでたどり着きました」
加治佐さんは、課題に直面したときどのように向き合うのか。
「真正面からぶつかって、当たっても砕けない派です。スマートとは言えないかもしれませんが、うまくいくまでひたすら粘り、やってやってやり抜いていると、次第にコツや道が見えてきます。大学院のときもそうでした。『東大生は頭で考えてばかりで手を動かそうとしない』と周りから言われていたことへの反発もあって、『それなら自分はひたすら手を動かしてみせる!』と、実験に人一倍打ち込んできました」
そのまっすぐぶつかるメンタリティは、いったいどこで培われたのか。尋ねてみると、ピッチャーとして打ち込んできた野球への取り組みにルーツがあるようだ。
「東大には、野球をするために入学しました。神宮球場で、プロ野球に進むような選手たちを相手に投げたい。その思いでマウンドに立ち、最初はこてんぱんに打たれましたが、諦めずに自分の課題をひとつずつ克服していくと、そういう選手たちも少しは押さえられるようになりました。速いボールを投げたいという我を捨てて、120 kmでもコントロールを少しでもよくする。カーブでもストライクをとれるようにする。欲を出さずに自分をダウングレードさせて基本に忠実に取り組むうち、戦い方のコツが少しずつ分かってきました」
4年間の戦績は0勝13敗。勝ち星こそなかったが、マウンド上でつかんだ確かな手応えが、「やってやってやり抜く」メンタリティを、「決して諦めない心」をつくり上げた。
その不屈のメンタルが、異分野を渡り歩く際の強い自信になったに違いない。
「大学院では生物学を研究し、就職先では半導体デバイスについて学び、再び戻った大学で、『界面』の研究に取り組みました。二つの分野を掘り続けた結果、地下で『界面』という鉱脈に遭遇した気持ちです。この地下鉱脈からの産物を地上にくみ上げ、世に送り出したい」
加治佐さんの目には、「やってやってやり抜いた」先の未来が、はっきり見えているのかもしれない。